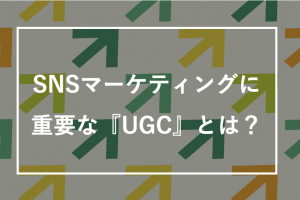AIはどこまでのことができるようになるのか
・これから進化し続けるのは「認識」「合成」技術などビッグデータの解析
・AIは人間の行うことすべて奪ってしまうのか
AIは感情を持つことができるようになるのか
・AIに倫理的な判断はできるようになるのか
・AIは人の感情を理解できるのか
AIで社会はどのように変化するのか~選択肢が増える社会に
全世界において開発が進められている人工知能(AI)ですが、今後研究が進められていくにつれて私たちの生活は便利で快適な生活を営めるようになると期待されています。しかしAIは今まで人間が行ってきた仕事を効率よく行うことができるようになることから、人間から仕事を奪い、失業する人が増えるのではないかと考える人も多くおられます。またAIが感情を持つようになれば、AIによって社会を管理するようになり、私たちはAIの管理下に置かれるようになるといった、都市伝説的なことを語られることもあります。今、AIの分野ではアメリカと中国での研究が、世界をリードしているといえますが、現時点においてAIの得意としている分野はビッグデータの解析であることは間違いありません。近い将来、AIはどこまでのことができるようになり、それによって社会はどのように変化していくのでしょうか。
AIはどこまでのことができるようになるのか
AIはさまざまなデータを活用して学習を自動化することができ、そこから何かを発見することが可能です。すべての作業を全自動で行うのではなく、大量にあるデータを活用したタスクを高い信頼性で実行することができるということです。つまり人の手によってタスクを与えてやる必要があり、その答えを得るためにAIを活用するのが人であるということになります。例えば近年の「指紋認証」「顔認証」技術の向上は、人の数だけ存在する指紋や顔から、その人だけにある特徴を抜きだすことが可能になりました。私たちの持つスマートフォンにおいてみても、私たちもAIの進化を感じずにはいられません。
・これから進化し続けるのは「認識」「合成」技術などビッグデータの解析
AIが得意としている作業は、「認識」「合成」といった特定の決まった作業です。その基となるビッグデータが大きければ大きいほど、AIの特性を活かすことができます。2016年3月、世界がAIの進化に震撼した出来事が起きています。それは囲碁のAIが、囲碁の世界チャンピオンとの5番勝負において、4勝1敗と大きく勝ち越したことです。それまで将棋やチェスのAIが人間に勝利するということはありましたが、囲碁は盤が広く、手順や変化も複雑であることから、「囲碁でAIが人間に勝つのは10年以上先」といわれていたのです。囲碁のルールをご存知の方であればお分かりになると思いますが、囲碁はその場面によって状況が変化しますから、これらをAIが認識するのは難しいと考えられていたのです。
このAIは「AlphaGo(アルファ碁)」と呼ばれているもので、Google DeepMindによって開発されたものです。Google DeepMindとはグーグル社傘下のイギリスのAI企業「ディープマインド社」であり、2015年でのヨーロッパ王者との対戦においても5戦5勝を収めていることで知られています。囲碁だけではなく、将棋やチェスなどにおいても優れたAIが開発されています。あらゆるビッグデータを解析することによって、今まで人が行ってきた作業よりもはるかに早く情報処理することができます。手間暇かけて行ってきたことは、すべてAIにとって代わられる時代が来ることは間違いありません。
・AIは人間の行うことすべて奪ってしまうのか
AIは今まで人の手によって行われてきたデータの収集や分析などについては、確実にとって変わる時代がやってきますから、そのような仕事や作業についてはなくなる方向だといえるでしょう。とはいえ、AIは「覚えること」「分析すること」は得意ではありますが、人間が行う意思決定や判断についてはできませんから、人間が行う作業をすべて奪ってしまうことにはなりません。2018年11月、北米放射線医学会(RSNA)によって刊行されている雑誌「Radiology」において、認知症を引き起こす原因となるアルツハイマー病の早期発見をAIによってできるようになったと発表しています。アルツハイマー病は我が国においても増加している病気で、認知症を引き起こす原因であるとして世界中で注目されています。アルツハイマー病のスキャン画像をAIに覚えさせることによって、平均して6年早くほぼ正確に診断することができたのです。
また認知症薬開発においてもAIが活用されており、開発された成分の特徴を解析することで薬の開発期間を3割程度短縮させることができるといわれています。そのため今後、急展開でアルツハイマーが解明される日がくるかもしれません。しかし多くのアルツハイマー病患者に対する治療は、人間の手で判断されることになります。AIが解析した結果をどのように活かすかについては、人でしかできないのです。
AIは感情を持つことができるようになるのか
これからAIの研究が進むにつれて、AIが人のように意思決定するようなことができるようになるのでしょうか。あるいは現在数多く実験されているコミュニケーションロボットが、感情を理解したり、AI自らが感情を持つようなことはあるのでしょうか。
・AIに倫理的な判断はできるようになるのか
冒頭からお伝えしている通り、AIは「認識」「合成」といった特定の決まった作業を行うことを得意としており、データのないものについて何らかの判断を行うことが不得意とされています。AIは顔の表情は体温の変化などを読み取って、ある程度、感情を感じ取る技術は持っていますが、その感情に配慮して忖度するような、臨機応変な対応を行うことは難しいとされています。先ほどアルツハイマー病に対する話をしましたが、アルツハイマー病を特定することや病気に適している成分を探しだすことはAIの得意分野であるといえます。しかしアルツハイマー病の人とコミュニケーションを図り、適切な医療や介護を行うことはAIができない部分であるといえます。アルツハイマー病の人の感情を掴んで、心に寄り添った介護を行うことは、これからも介護スタッフでなければならないのです。そのようなことを考えると、AIが今後どんどん発達することによって、人間らしい人間でしかできない部分だけ、私たちが行うような社会になっていくのでしょう。
・AIは人の感情を理解できるのか
感情解析の分野については世界中で研究されており、我が国においても株式会社Empath(エンパス)がコールセンター事業を行う株式会社TMJとの事業提携において音声で感情解析するAIを開発しています。この音声感情解析AIを開発したことによって、コールセンターで働くオペレーターの品質向上とオペレーターの離職率の高さを改善させることに成功しています。音声で感情が解析できることによって、リアルタイムでAIからオペレーターに指示を出し、顧客の感情に寄り添った適切な対応ができるようなることで成約率が高まることが期待できます。またオペレーターの離職率の高さは課題となっていますが、メンタルヘルスの観点から見てもAIが感情解析できることは上司などのサポートを速やかに受けることができる仕組み作りになります。このAIは自らが感情を持っているものではありませんが、人の感情を読み取ることができることを考えれば、感情に近いものを持っているといえるのかもしれません。
AIで社会はどのように変化するのか~選択肢が増える社会に
アメリカは常に世界経済をリードしてきました。これからも世界経済の中でリーダーシップを保つために、調査・開発をし続けていくつもりでしょう。特にAI研究においては、AI企業が柔軟性を持ってイノベートできるような環境が、国家戦略の中で整えられています。そのため今までの枠組みを超えて、これからの経済を発展させるための調査・開発が可能なのです。また経済大国を目指す中国は、AIの開発が経済発展に大きな影響をもたらすものであるとして注目しており、国家主導のもとに「次世代AI発展計画」を発表しています。中国では近年、労働人口の減少や経済成長による賃金上昇が懸念されていますが、このような社会問題をAIの開発によって解決しようとしています。特に13億人という巨大な人口による大規模なデータがありますので、中国企業はこれらのデータを活用し技術進化・経済発展のために研究・開発を行っているのです。
AIの研究や開発が進むにつれて、私たち人間が手間暇かけて行ってきた作業を瞬時に行えるようになるため、単純作業や重労働はどんどん減っていくものになるのは間違いありません。だからといって、単純作業や重労働が完全になくなっていくのではなく、AIに任すことができる、人がやらなくていいという選択肢が増える社会になっていくのだといえます。アメリカで増えているコンビニ「Amazon Go」では、入店や商品の決済、商品の販売予測や発注にAIを導入しましたが、通常のコンビニよりも店員が多く配置されていることが知られています。これは人にしかできないコミュニケ―ションやサービス向上に努めているためです。つまり人が豊かになるためにAIを導入している例であるといるでしょう。AIでできることが増えることは、同時に私たちに選択肢が増えることになり、社会での生活が豊かになることをあらわしているのではないでしょうか。
【参考】
囲碁の最強人工知能AlphaGo(アルファ碁)の仕組みとは? TECH NOTE
https://tech-camp.in/note/technology/32855/
「Radiology」北米放射線医学会(RSNA)
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2018180958
薬開発 AIで早く アステラスなど、効能を予測 期間最大3割短縮 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34320240Y8A810C1EA1000/
株式会社Empath「声ダケノ感情認識テスト」
日本経済新聞社 アマゾン・ゴー 無人の可能性は無限大
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO34388550R20C18A8H46A00/
総務省 欧米におけるAIネットワーク化に関連する政策・市場動向
http://www.soumu.go.jp/main_content/000414765.pdf
日本総研 人工知能(AI)強国を目指す中国
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/10456.pdf